NEWS/REPORT 新着情報
心が少し疲れたら―浦河で待っている、やさしく受け入れてくれる場所

2025夏のインターンシップできてくれたミヤビさんの記事。
外から見るのと中で見ているのとは異なる。自分の「あたりまえ」は他人の「あたりまえ」とは限らない。という前提から地域の人に知ってもらいたい事を書いてくれています。じつは「ありがたい」事。ありがたいとは、漢字で書くと「有り難い」と書き、「有ることが難しい」という意味です。言いかえると「貴重なこと」。
外からきた若者達は私たちに「あたりまえ」となって見えなくなった「ありがたい」事を再認識させてくれるのです。私たちは「ありがたい」事をみがき、育み、次の世代に誇れるようにしてゆくことがこの地域を守ろうと思ってくれる次世代をつくることにつながります。バトンを渡すのではなく、バトンを受け取りたいと言ってもらう環境をつくるのも地域工務店の役割のひとつと感じています。
浦河町には、べてるの家という精神障害等をかかえた当事者の地域活動拠点がある。精神障害等の治療は、薬のみによる治療、もしくは薬を服用しつつ施設内または狭い地域内での生活を患者に強いることが多いイメージがあるが、浦河町にはそういった治療を好まない精神科医の方がいらっしゃるそうだ。そのお医者さんは症状の半分を薬で治すが、もう半分は地域の人でその方を支えるor人の力で治すことを治療の上で大事にしている。この治療法が効果的なのか、べてるの家で活動する精神障害者の方のご家族が移住されたり、この施設で働きたいと精神科関係の方が浦河町に住まれたりすることがあるようだ。実際、ゲストハウスまさごにて、大学の講義でべてるの家のことを知り、より深く学ぶために浦河町に一人旅に来ていた福祉系を学ぶ大学生の方とお話しすることができた。私は福祉や精神障害等についての知識はほぼないがその専門分野では一目置かれた施設だということが推察できる。
べてるの家では、まず施設の患者の方が話す不安や不満を職員の方が聞いて、一度受け入れる。このように一緒に問題を共有して、そのことについて考えつつ、その人にできる仕事(地元の名産、昆布の梱包作業など)を任せて、障害者雇用に繋げ、精神障害を持っている方のできることを増やす。ここの商店街にはべてるの家の方が働くレストラン(カフェぶらぶら)もあるようだ。
精神障害等を持つ方々を、牢獄のように閉じ込めることなく、いきいきと自然の多い浦河町で生活をしてもらう。そして症状が街中で出たとしてもそれを受け入れる。浦河町では精神障害を科学の力で改善するのではなく人の力で行うのだなと個人的に感じた。確かにそれは科学の力を使うよりも時間や手間のかかる長い道のりなのかもしれない。しかし、その人の個性・その人らしさに敬意を払いつつ、社会に溶け込めるように人と地域の力で導いていく、その治療理念が素晴らしいと素人ながらに感じた。
ここで、私が大学2年の時に受講していた地方行政についての講義を思い出した。その講義では、現職の地方公務員(保健)の職員の方が、今後の少子高齢化社会、そして高齢者の方(特に認知症の方に焦点を当てている)に対する地域の人々の対応について話をしていた。「少子高齢化になっていくと介護のための人手がどんどん少なくなっていく。だから、認知症は地域の人々の力で発症を遅らせ、発症した場合は支えることが必要になってくる。認知症の方に対して、まず相手の言うことを否定してはいけない。ひとまず相手の話すことを受け入れてそれから是正していく。認知症の人は意外と少し話すだけでは認知症だとわからないものでもある。そして、その地域の人々が認知症の人を理解し支える意識(ゆっくり話しかける、相手のペースに合わせる、相手に対してゆったりとした動きを心がける、認知症への理解を深めるなど)を持ち行動に移すことで認知症は悪化を遅らせ、介護なしで生活することができるようになる。」といった趣旨の話だった。もともと、地域の人々のつながりが強固な町だと思うので、その時点で認知症の予兆が出たとしても進行を遅らせ不ことができるのかもしれないが、この町では精神障害等のハンディキャップだけでなく認知症の方も生き生きとその人らしく自由に暮らしていける価値観・文化が根付いているのではないかと感じた。
追記
後日、前述したカフェぶらぶらでランチを食べた。店内にはべてるの家に関する本がたくさん置いてあり、自分を責めすぎている人、生きていて息苦しさを感じる人などに是非読んでもらいたいという本が沢山あった。そういった方々にも、べてるの家の取り組みや運営にあたる先生の話が届くことを切に願う。

浦河町から
全ての人の人生を 豊かにする仕事を
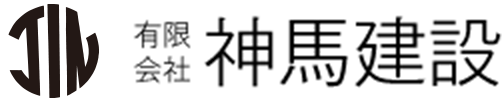
- 〒057-0032
北海道浦河郡浦河町向が丘西1-539-45 - FAX. 0146-22-3923